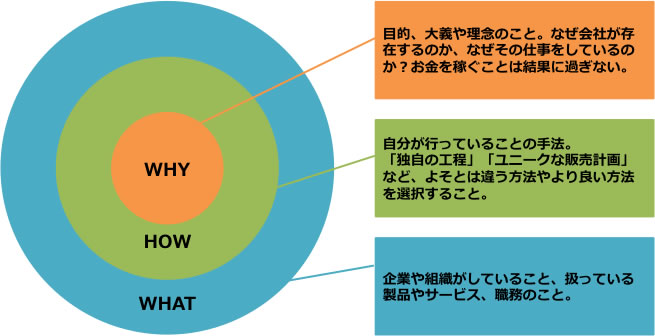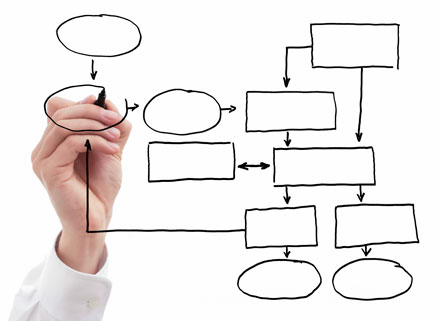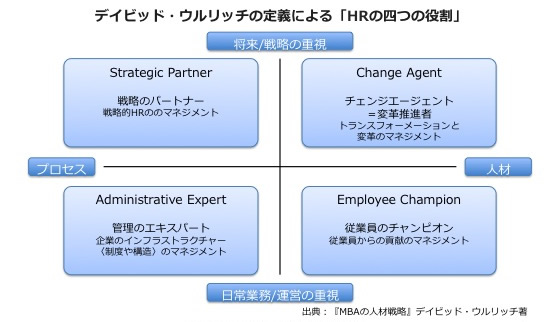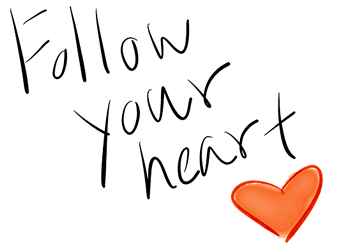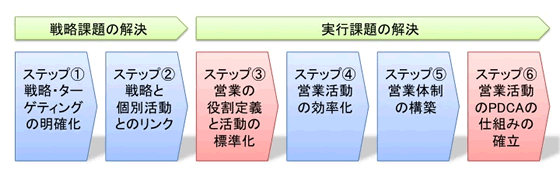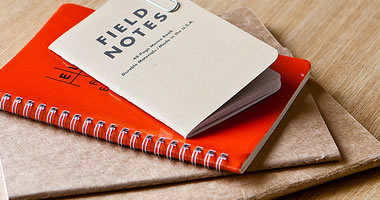柴田励司さんの著書、「「仕事力」のある人、ない人」を読んだ。
本書は仕事力を高めるヒントを50項目にまとめたものだ。
個人的に気になったのは以下の二つだった。
①「信頼される」リーダーへの道
部下の「よくない点」を嘆き、文句を言う前に、輝く部分をさらに輝かせるような環境を作ることができていないことを反省すべきでしょう。
(中略)
また、マイナス点を認識し、注意することで、部下に対して「私があなたの上司ですよ」というポジショニングを示した気になっているわけです。
(中略)
上司としては、誰にでも弱い部分はあること、デキない点があることをしっかり踏まえたうえで、デキる点に、超大きなスポットライトを当てて、部下に達成感を感じながら仕事をしてもらいましょう。
これは最近強く感じる。
ただ、どっちかというとリーダーではなくマネジャー的な役割だと思うが。
社員がモチベーションを発揮し、高い生産性を発揮できるのは、
●自分が組織に必要とされ、評価されている
●自分の強みが活かされている
この二つが満たされているときだと思う。
ではマネジャーの仕事は何かというと、メンバーが強みを発揮しないことを嘆くことではなく、メンバーの出来ない部分を叱ることでもない。
そんなことをしてもその人は自尊心を見失い、モチベーションを落とすだけだ。
まずはメンバーが自分の強みを発見する手助けをし、それを発揮できるような職場を作ること。
そしてメンバーの成果に対して、出来た部分を最大限に評価し、感謝の意を伝えた上で、「But I know you can do better」と、さらなる期待を伝えることだ。
その時その時の努力や成果、他の人との比較によってではなく、その人自身を絶対的に認め、信頼してくれる人が一人でもいれば、その人は心から勇気付けられる。
そして、その期待に答えようとがんばることができるのだと、最近気づく場面があった。
その人が自分の成長をちゃんと確認できるようにマネジメントしてあげ、そして成長した部分について最大限に褒めてあげると、その人はますますがんばるようになり、どんどん成長していくのだ。
すると次第に自分に自信を持ち、自尊心が生まれ、さらには自主性が生まれてくる。
何か頼みごとをするときも、前なら無表情で「わかりました」だったのが、自信満々に「任せてください!」なんて言うようになる。
前はできなかったことが、気づいたら自分でできるようになっていたりする。
マネジャーの対応で、こんなにも人は成長できるのかと、ちょっと感動的な体験だった。
②人の「情報」の取り扱い方
発言内容、単語、言い方、タイミング―これらは聞いている人の感情に揺らぎを与えます。組織は「機能の集合体」のように見えて、実は「感情の集合体」です。リーダーの機嫌がよければ組織が明るくなり、リーダーがどよんとしていれば組織もどよよんムードになります。
確かに、組織のトップにいるような人が常に暗い顔をしていると、「社長があんな顔をしててこの会社は大丈夫なのか?もしかしてヤバイんじゃないか?」と社員も不安になってしまうだろう。
また、常にというわけではなくてもリーダーが暗い顔をしていたら、それは部下にも伝染してしまう。
ポジティブであるということは、確かにリーダーの重要な資質のようだ。

 ホーム
ホーム 管理人について
管理人について ブログ記事
ブログ記事 スティーブ・ジョブズ
スティーブ・ジョブズ 業務改革/BPR
業務改革/BPR IT/ツール
IT/ツール ビジネススキル
ビジネススキル 読書/勉強法
読書/勉強法 ワークスタイル
ワークスタイル 管理人の日記
管理人の日記 雑学ネタ
雑学ネタ コンタクト
コンタクト






 正々堂々と
正々堂々と 営業の話とは程遠い。
営業の話とは程遠い。

 ぴんとこず
ぴんとこず