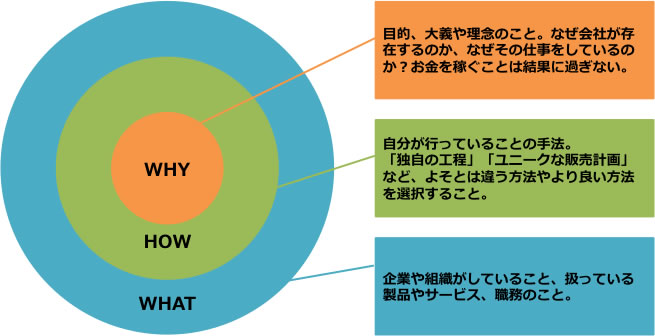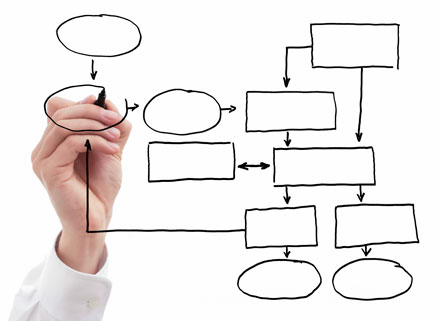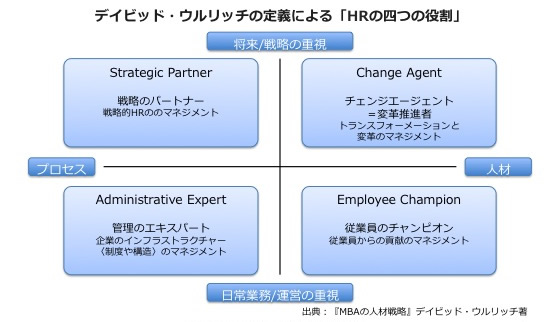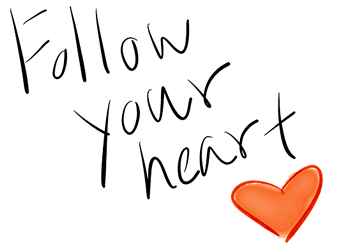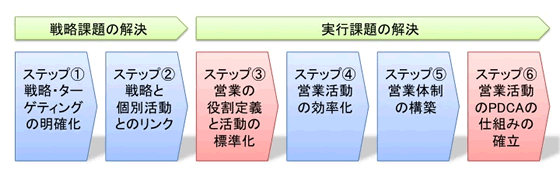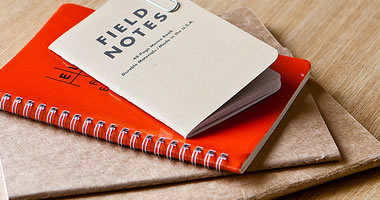つんく♂ さんの著書、「一番になる人」を読んだ。
「この本はやばい…!」というのが、読んだ後の率直な感想だ。
私は小学校高学年から中学校までの間シャ乱Qのファンで、今でもシングル曲は全部持っている。
それで興味を持った本書だが、読んで本当に良かった。
私から見ればつんく♂ さんは大成功をおさめた人物だ。
しかしつんく♂ さんは自身を凡人だと断言し、凡人だからこそ天才をとことん研究し、どうすれば自分も一番になれるのかを考え抜いた結果、今の自分があるのだという。
凡人だと自覚しながらも、暗中模索の末に自分の好きな分野で一番になってみせたつんく♂ さんの哲学からは、同じく凡人である私を含む多くの人々にとって必ず学ぶべきところがあるはずだ。
1.「すべては妄想から始まる」
つんく♂ さんが自身がミュージシャンとして活躍している姿を妄想したように、私たちの多くも妄想を描く。
では、妄想を現実に変えられる人と妄想のまま終わる人の違いは何かというと、それは妄想を実現させるまでの過程も妄想できるかどうかだったのだ。
妄想を頭の中においておくだけだからただの妄想に終わってしまうのであって、人前で宣言することで妄想は立派な「計画」になり、「予定」になると考えたのです。
一見、たわけた妄想も、そこに至るプロセスを細かく分解していくと、「ビラを毎日、配るだけ」という誰もができる単純作業に行き着いたのです。
(中略)それでも百をめざして努力すれば、少なくとも十くらいまではたどり着ける。運や風向きがよければ、百を超える可能性も出てきます。
最初は妄想でいいのです。
充分に妄想を楽しんだら、次にはそれを実現させるための方法まで具体的に妄想してください。具体的なイメージができてきたら、それはイメージトレーニングとなり、夢を実現していくうえでの青写真となるのです。
私は目的がありつつも、それを実現していく過程をいまいちイメージすることが出来ずにいる。
本に何かヒントがあるのではとも考えたが、そうではなく、私には「妄想力」が足りなかったのではないか。
やるべきことは分かった、一日30分妄想である!
「ビラを毎日、配るだけ」になるまで、妄想あるのみ。
2.天才を徹底的に研究する凡人が天才を超える
シャ乱Qもデビュー後の2年間は全く売れない時期が続いた。
その時つんく♂ さんは自分が凡人であると気づいたそうだ。
自分と同じ分野の天才を前にした場合、人間の心理は二つに分かれると僕は思っています。
彼らは天才だから、自分とは出来が違うんだと思ってしまう人。
彼らは天才だから、少しでも彼らに近づけるよう、彼らを研究してみようと思う人。
つんく♂さん さんは後者だった。
同じ凡人でありながら売れている人や、天才を研究することで、どうすれば自分も売れる凡人、売れるプロになれるのかを考えたのだそうだ。
天才と呼ばれるほどの人は、あるとき素晴らしい曲や詞といったものが天から降りてくるのかもしれません。
でも、僕のような凡人、天才でない人間はそのノウハウを研究し、コツコツやっていくしか道はないのです。
天才が三回でできることを、凡人は百回、二百回と練習しなければならない。
しかし、百回、二百回と繰り返すからこそ、天才には見えてこない「コツ」や「ツボ」が見えてくる。
それを人に教え始めると、ますますノウハウが洗練されていく。
つんく♂ さんがシャ乱Qで手にした成功を、同じくプロデューサーとしてモーニング娘でも実現できたのは、自分のノウハウを洗練させてきた経験があったからこそだったのだ。
天才は一瞬まぶしい光を放つが、何曲も曲を作っていればいずれネタがつき、才能が括弧する。
しかし凡才は元々才能がないがゆえに、才能が括弧することはなく、むしろじわじわと増やしていける。
そして、いずれは天才をも超えるかもしれないのだ。
3.好きなことだからこそ没頭できる
改めて、好きなことを見つけることの大切さを確認させられた。
よく間違えることだが、「好き」と「得意」は別なのである。
けれど、どんなに「得意」なことでも、「好き」という感情にはかなわない。
(中略)
何かを好きになる。その瞬間、人はそのことに関して、抜きん出た存在になる。
(中略)
子どもにしろ、大人にしろ、人は好きなことには、全身全霊で取り組むことができます。(中略)それは決して努力してだせるものではありません。しょせん「努力」で出せるエネルギーは、「好き」で出せるエネルギーの比ではないのです。
(中略)
「一番になる人」は例外なく、「好き」をとことんきわめた人といえます。
私はスティーブ・ジョブズの“The only way to do great work is to love what you do”という言葉に強く影響を受けたのだが、本書を読んで、好きなことだからこそ進んで自分の全エネルギーを注ぐことができるのだと改めて思った。
ある意味、ある対象に対する愛情こそが、最大の才能なのかもしれない。
音楽に対して「好き」という感情を持っていたつんく♂ さんは、そういう意味でまぎれもなく天才だったのではないか。
成功している姿を妄想するのが楽しくて仕方がなくて、そこにいたるまでの道筋も妄想することができて、それを実現するためにはそれこそ成功者を徹底的に分析して、百回でも二百回でも練習をすることになったとしても惜しくはない。
そう思えるような対象を見つけた人こそが、「一番になる人」なのだなと今確信した。
他にも「アメーバのように生きる人」という、やはり自分の理論に固執することなく素直になることが大切なのだなと感じさせるテーマや、「サクセスストーリーはピンチヒッターからはじまる」といった、面白いテーマがいくらでもある。
是非、読んでみてください。
以下、私用メモ
●失敗やトチリの妄想は、それを回避する方法や注意を促してくれる
●二時間のステージをイメージするのに二時間かけるくらいシミュレーションする
●自分はこうだという枠を決めず、アメーバのように生きる
●人が面倒くさがるような仕事にこそ、大きな宝物がある
●自分のやりたいことだけをやってきたわけではない、サクセスストーリーはピンチヒッターから始まる
●自己の満足は大衆の満足ではない
●締め切りは、人間の力を目一杯に引き出す装置
●突っ込まれるシロを持つ
●何か分からないけど不安だと、恐れながら道を進むのは、気持ちにブレーキをかけながら進むのと同じ。むしろ、不安材料を全て書き出し、そうなったときの対処法を書いておいて、安心して全力で挑む

 ホーム
ホーム 管理人について
管理人について ブログ記事
ブログ記事 スティーブ・ジョブズ
スティーブ・ジョブズ 業務改革/BPR
業務改革/BPR IT/ツール
IT/ツール ビジネススキル
ビジネススキル 読書/勉強法
読書/勉強法 ワークスタイル
ワークスタイル 管理人の日記
管理人の日記 雑学ネタ
雑学ネタ コンタクト
コンタクト








 会計のイロハ本
会計のイロハ本 小さな会社でもやっていけるという勇気を貰いました
小さな会社でもやっていけるという勇気を貰いました
 疲れる文章…
疲れる文章…
 締め切りだけは絶対に守る
締め切りだけは絶対に守る